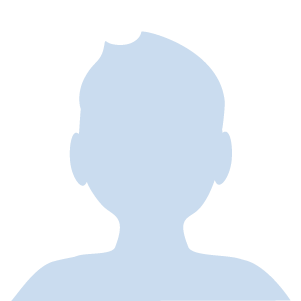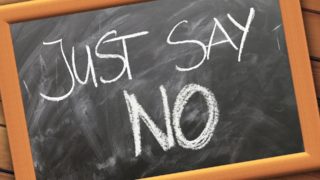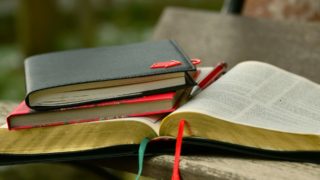キャリア プラン
キャリア プラン・会計事務所と企業の経理はどっちがいいの?
・税理士業界のキャリアプランを教えてください。
こんな悩みにお答えするため、税理士のキャリアプランについて解説する記事を用意しました。
ここで解説する税理士の基本的なキャリアプランを知っておけば、税理士としてどのようなキャリアを歩みたいか、いま何をしなければならないかをイメージすることができますよ。
僕はBig 4税理士法人や大手会計税務コンサルティングファームでの経験があります。
また、大手総合商社や金融機関で税理士法人を活用する立場にもあったことから、税理士業界では幅広い交流があります。
結論から先にお伝えします。税理士のキャリアプランとしては、主に以下の4つに分類されます。
税理士のキャリアプラン
① 税理士事務所勤務
② 社内税理士
③ 独立
④ その他(海外やコンサルティングファームなど)
どのキャリアを歩みたいかによって、いま何をすべきか・どのような学習をしていくべきかだけでなく、将来の働き方も変わっていくので、じっくり読み込んでくださいね。
それでは、4つの分類について解説していきますね。
📓もくじ
キャリア(1):税理士事務所勤務
もっとも一般的なキャリアは、税理士法人や税理士事務所で、税理士というプロフェッショナルとして働くケースです。
ようやく取得した難関資格である税理士資格。それを生かして働きたいと考える人は多いはず。
現在では多くの税理士法人・税理士事務所が存在します。最大手であるBig 4税理士法人から国内大手の税理士法人、相続や事業承継などを強みとする個人事務所など、それぞれが強みとしている分野や特徴を有しています。
したがって、働く側としても、どのようなスキルを身に着けたいかに応じて、柔軟に働く環境を変えられる業界と言えます。
メリット①:先生という貴重な立場
税理士も、弁護士などと同じく『先生』と呼ばれることがあります。それは、『税理士は企業のお医者さん』と考えている人も多いように、困った時や出来ないことに遭遇したときに助けてくれる存在だからです。
従って、特に中小企業がクライアントの場合には、その企業の社長や役員レベルの人たちとやり取りする場面が多く見られます。テレビや雑誌で見たことのある経営者とお会いすることもあります。
そうした方々から『先生』と頼られる立場であることは、強いやりがいを感じられるのではないでしょうか。
また、そうした環境であるため、仕事に対するやりがいだけでなく、クライアントからも勉強させて頂く機会や、自分自身が責任感を強く感じる場面もあるでしょう。
そうした環境は、アドバイザー、専門家である税理士の醍醐味の1つと言えます。
メリット②:プロとしての専門性を磨ける
税理士は、基本的には税務や会計またはその周辺知識を武器としています。
昨今の税法や会計基準は、企業のグローバル化の加速や取引の複雑化に伴って、より専門性の高いものになってきています。
それに伴い、税理士も日々変わり続ける税法や会計基準、その周辺知識を勉強し続けなければならないため、日々の業務の中で成長を感じられる人も多いはず。
成長を感じられる環境によって、一人のプロフェッショナルとしての自信が持てます。
メリット③:将来は独立も可能
税理士資格を取得した人は、誰しもが一度は独立を夢見るのではないでしょうか。
税理士資格には、年齢による執行がありません(今のところは)。
従って、今は会計事務所や税理士法人で働きつつ、定年後に独立し、ゆっくりと生活することを望んでいる人もいます。
『人生100年時代』、『老後2,000万円』と言われるこの時代に、将来の独立に向けて働くこともやりがいを感じられるかもしれません。
スタディング|難関資格・国家資格を目指す方のためのオンライン資格講座
ジャスネットキャリア【アカウンタンツライブラリー】|税務知識や日商簿記3,2級など経理に役立つ100講座が学べる動画サイト
月額定額サービス【ウケホーダイ】|様々な資格学習が980円でウケホーダイ
※リンクをクリックすると、公式サイトへ飛びます。
デメリット①:常にプレッシャーを感じる
税理士は他の人のお金を扱う仕事です。
また、クライアントが税法という法律を守るために適切なサポートするのが責務です。
従って、もしクライアントが出来そうになければ代わりにやってあげなければならないし、期限に間に合いそうになければ何とか間に合うようにサポートしてあげる。税理士の仕事は、非常に責任感のある仕事なのです。もし法律を守れなければ、クライアントは追加納税と言う余計な支払いをしなければならなくなります。
さらに、複雑化する税法にも、もしクライアントから聞かれたら何とか調べて答えなければなりません。
その意味で、税理士と言う立場で働く事は、常に高いプレッシャーの下で働くことを意味します。
デメリット②:常に勉強
上記でも説明した通り、昨今の税法や会計基準は、企業のグローバル化の加速や取引の複雑化に伴って、より専門性の高いものになってきています。
それに伴い、税理士も日々変わり続ける税法や会計基準、その周辺知識を勉強し続けなければならないため、日々の業務の中で成長を感じられる人も多いはず。
もし、最新の税務情報を勉強するのをやめてしまえば、法律においてかれることになります。それが意味するのは、税理士としての終焉とも言えるかもしれません。
したがって、税理士として生きていくと言う事は継続的な勉強はマストなのです。
デメリット③:スケジュールはクライアント次第
特に上場企業やその子会社など、比較的大きな規模の法人をクライアントとしている場合、スケジュールはクライアント都合になりやすい。
もちろん、働いている事務所に人材が豊富なのであれば問題ないが、大抵の場合、そうではない事務所が多いと思われます(これだけ売りて市場ですからね)。
その場合、医者や弁護士と同じく、クライアントが困ったときには深夜でも週末でも祝日でも、対応してあげなければならないケースが出てきます。
キャリア(2):企業内税理士
企業内税理士とは、税理士資格は持っている(企業によっては登録もしている)ものの、一般企業の経理部や税務課などで通常の会社員として働くことを言います。
近年、弁護士資格を持つ企業内弁護士や公認会計士が増えているのと同様に、企業内税理士も非常に増えています。
メリット①:企業の内部資料や作成プロセスを学べる
実は、一般事業会社の経理での業務経験なく、税理士事務所で働いている人によく見られる欠点の1つが、このポイントだと考えています。
税理士は、税務申告や意見書を作る際、まずはクライアントから必要資料を入手する必要があります。ここで問題となるのは、一般企業の経理の経験がない若手税理士は、
・ 社内にどのような資料があるのか
・ 社内でどのようなプロセスで数値が報告されているか
を知らないため、税務申告や現象を作るための必要かつ最適な情報を得られない人が多いのです。
そのため、一般企業で、決算や税務申告に必要な数値がどのように作られ、どのように管理され、それがどのように税務申告書に落とし込まれるのかを理解していれば、クライアントからすればより具体的かつ明確な資料依頼がされるので、資料準備の手間がだいぶ省かれます。
これは、税理士が仕事をする上での基本とも言えることだと考えています。
メリット②:社内で重宝される
一般的に、新卒で一般事業会社に入社した社員は、まずは経理を学び、そのあとで税務を学ぶことになります。
しかしながら、一般の会社は、数年単位で異動になることから税理士事務所で働いている人と同じレベルにまで教育することは非常に難しく、ナレッジが蓄積しない会社が多くあります。
そのため、税理士の立場で実務経験を積んだ人材は、社内でも貴重な存在として重宝されます。(もちろん、それだけの知識やスキル、経験を有していることが前提です)
メリット③:経理部長やCFOなどのポジションを狙える
さらに、税理士として事業会社で働く醍醐味の1つと言えば、企業の経理部長や財務部長、さらにはCFOを目指せる点が挙げられます。
近年は、特にグローバル規模でのタックスプランニングや税務コンプライアンスの向上、税務ガバナンス構築などが、ESG評価を始めとする企業価値評価の上で重要視されつつあります。
そのため、特にメガベンチャーや成長著しい産業においては、将来のCFO候補として、税理士に対する求人がかなり増えています。
デメリット①:税務知識・スキルが衰える
率直に言えば、一般企業の経理部や税務課にいるよりも、税理士法人や会計事務所で働いている方が、圧倒的に税務知識は蓄積されます。
言い換えれば、一般企業の経理部や税務課にいると、税務知識や実務的なスキルがどんどん落ちます。
もし仮に落ちないとしても、知識やスキルは、その企業における税務上の課題や申告書上の問題に限定されるため、税務のうち1部の分野しかよくわからなくなっていきます。
したがって、企業内税理士として長期的に一般企業の会社員をしていくのであれば、資格は持っているものの、プロフェッショナルとしてのスキルはある程度諦めた方が良いでしょう。
デメリット②:プロ意識が減る
社内税理士として一般企業で働くと、普段やり取りする相手は、これまでのように外部のクライアントではなく、基本的には社内の人たちになります。
社内の場合、ある程度わがままを聞いてもらったり、甘えが出てしまったりもします。
それに、自分が税務の分野では1番という環境になりますので、プロフェッショナル意識を持って継続努力していくには、かなり強い意志が必要になります。
結果的には、日々クライアントと接したときに比べれば、プロフェッショナル意識は減っていくことになるでしょう。
デメリット③:営業力や提案力が減る
上記と同じように、日々社内の人とばかり接するようになると、これまでのクライアントとのやり取りで培ってきた営業力や提案力は減ってしまいます。
税理士の場合、一般企業に入るのであれば、通常は経理部や税務課に配属されることとなります。
経理部や税務課は、会社の営業活動の結果である数値を集計し、決算書や税務申告書に落とし込むのが基本的な役割です。
もし新たな管理体制や、節税対策を考案したとしても、それは基本的には経理部や税務課の中で処理されることから、広く多くの人に何かを説得したり、訴えかける機会はなくなります。
したがって、これまで培った営業力や提案力は下がってしまうと考えた方が良いでしょう。
【リクルートエージェント】|一般公開している求人の他、10万件以上の非公開求人がある最大級の転職エージェント。応募が殺到するため一般公開できない重要求人なども取り扱ってます。職務経歴書・履歴書などの書類の添削、独自に分析した業界・企業情報の提供なども無料で行ってくれます。
転職なら【doda】|大手総合転職サイトで税理士業界の転職に一番力を入れているのがdoda。全国多くの事務所の求人あり。
マイナビ税理士
MS-Japan
※リンクをクリックすると、公式サイトへ飛びます。
キャリア(3):独立
次に、税理士として一度は考えるであろう『独立』について解説していきます。
メリット①:一国一城の主人になれる
最難関国家資格の1つである税理士資格を取得したからには、その資格を十分に生かして働いてみたいものですよね。
税理士業とは、税理士法で守られた税理士や特定の弁護士などしかできない独占業務なのです。
「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とすることをいう旨規定されています。
1 税務代理(法第2条第1項第1号)
税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)をいいます。
2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。
3 税務相談(法第2条第1項3号)
税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。
(国税庁「2 非税理士により行うことが禁止される税理士業務」より)
それに、税理士として独立する場合、初期投資はほとんどかからず、在庫も全く抱えないため、もし失敗したとしてもリスクはほとんどないと言えるでしょう。
したがって、自分の会社を持ちたい・独立してみたいと言う人にはオススメな選択肢といえます。
メリット②:自由な働き方ができる
独立した場合、多くの従業員を雇ったり、1人で個人事業主としてやっていくなど、いろいろなケースがありますが、現代においては、基本的に在校や店舗を抱えずにやっていくことも可能ですので、自分の思い通りの働き方を実現する方法の1つとも言えます。
それに、現在の働き方改革の推進や多様化により、近い将来、税理士の働き方も変わるかもしれません。
一部の大手税理士事務所などでは、忙しい時期だけ、業務委託と言う形で独立した税理士を雇うケースも増えています。
メリット③:定年がない
さらに、税理士資格には年齢による失効がありません。
これは、税理士業界の課題の1つでもあり、平均年齢を引き上げる原因ではありますが、最難関国家資格のメリットともいえます。
『人生100年時代』『老後2,000万円』とも言われているこの時代において、いちど独立してしまえば自分が働きたい・働けると思っている限り働けるのは、安心材料の1つといえます。
デメリット①:競争が激しい
近年、税理士試験の受験者が減る一方で、税理士法人の数が増加しています。
これまでは、税理士事務所の数もそれほど多くなかったため、独立すればある程度は稼いでいけるような業界と言われていました。
ですが、現代においては、強みや特徴がないと他の税理士法人や会計事務所と差別化ができないくらい競争が激化しています。
したがって、独立するためには、他と差別化できる位のスキルや経験を磨いた後か、重要なクライアントを引き継ぎながら独立することが大切です。
デメリット②:人材の確保が難しい
税理士試験の受験者数が年々減少していることから、もし事業が拡大していったとしても、優秀な人材を採用するのが非常に難しい状況にあります。
また、そのような状況で経営を続けていると、従業員にしわ寄せが生じます。残業時間が増えたり、休日出社が増えたりと、従業員がやめてしまう理由が発生してしまうかもしれません。
これは、税理士業界の今後の課題の1つでもありますが、独立した時に必ず直面する課題と言っても過言ではありません。
デメリット③:後継者がいない
もしあなたが独立して成功したとして、あなたのお子さんが必ずしも税理士となるとは限りません。
また、税理士試験の受験者が年々減っていることから、必ずしもあなたが雇っている従業員の中に税理士がいるとも限りません。
そのため、独立したときには後継者問題がついて回る可能性が高いため、早めに対処することが望まれます。
キャリア(4):その他の働き方
最後に、その他の選択肢として、海外で働くことや、コンサルティングファームで働くことが挙げられます。
ここでは、それぞれについて簡単に説明しますね。
例①:海外で働く
日本企業の海外進出とともに、税法のグローバル化が進むことで、日本の税理士として海外で働く人も増えていますし、需要も伸びています。
昨今、特に国際税務の分野においては日本企業の海外進出とともにより複雑化が進み、日本の親会社だけで適切な税務申告を実現することが難しくなってきています。
日本企業のグループとしてのコンプライアンス意識の向上や、日本の親会社のガバナンス体制の構築を目的に、現地に日本の税法を熟知したアドバイザーが求められているのです。
例えば、大幅な税制改正が進むタックスヘイブン税制(CFC税制)においては、日本の申告のために必要な情報を現地の子会社から報告してもらう必要がありますが、親会社もすべての取引を熟知しているわけではありません。
一方で、その子会社も日本の税法を知っているわけではないので、適切な判断を行いません。そういった場合に、日本の税法を知っている現地のアドバイザーが重宝されるのです。
例②:コンサルティングファームへ転職
Big 4税理士法人や大手税理士法人で、上場企業や外資系企業をクライアントとしていた人の選択肢として、戦略系や総合系コンサルティングファームへの転職が挙げられます。
もちろん、いくら大手税理士法人で勤務していたとしても、初めての業界になるため若手のポジションからのスタートとなることが多いでしょう。
しかし、昨今の各国税法のグローバル統一化や複雑化により、大手企業を相手とするコンサルティングファームでは、国際税務や連結納税等の高度な税務知識が求められるようになります。
また、総合系コンサルティングファームにおいても、M&Aや事業承継では組織再編税制や税務デューデリジェンス等の知識や経験が必要になります。
したがって、高度な税務知識をもった人材であれば、コンサルティングファームへの転職も需要が高まってきているのです。
さいごに
以上のとおり、税理士試験に合格したら・税理士となったあとのキャリアとしては主に以下の4つが考えられます。
① 税理士事務所勤務
② 社内税理士
③ 独立
④ その他(海外やコンサルティングファームなど)
これらは、「どのような顧客を相手にしたいか」や「どういった分野を強みにしたいか」、「どういった働き方をしたいか」などによって変わると思います。
そのため、慎重に判断すべきです。
ただし、税理士業界の良い点の一つとして「転職に前向き」ということが挙げられます。もし違ったと感じたならば、転職してキャリアアップしていくことも可能ですので、「いま人生を決めなきゃいけない」など構える必要はありませんよ。
そういったときのためにも、これを読み終わった人は、ひとまず転職サイトに登録してより自分にあった環境を探してみましょう。転職サイトには、これから税理士試験を頑張る人や、いま試験を頑張ってくれる人にもあった会計事務所や税理士法人の求人も掲載されています。
企業情報がメールで届いたり、無料で転職の相談ができます。いずれも5分ほどで登録できますよ。
【リクルートエージェント】|一般公開している求人の他、10万件以上の非公開求人がある最大級の転職エージェント。応募が殺到するため一般公開できない重要求人なども取り扱ってます。職務経歴書・履歴書などの書類の添削、独自に分析した業界・企業情報の提供なども無料で行ってくれます。
転職なら【doda】
マイナビ税理士
MS-Japan
※リンクをクリックすると、公式サイトへ飛びます。