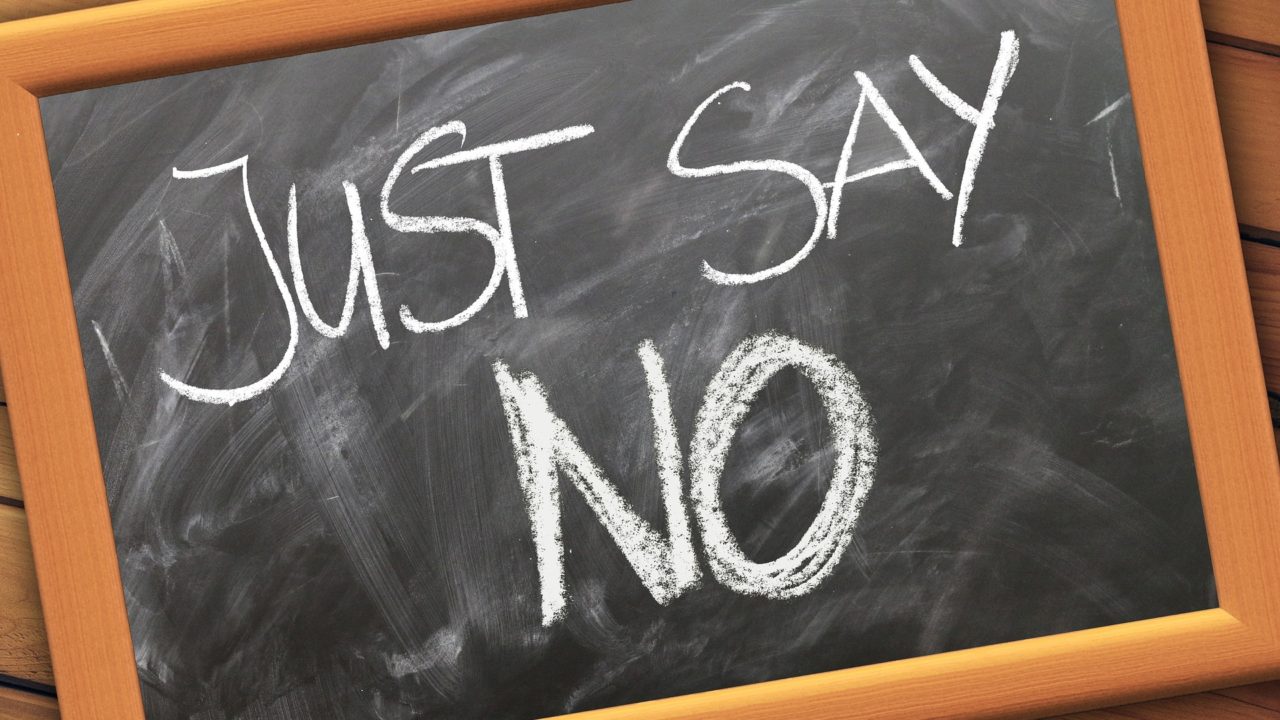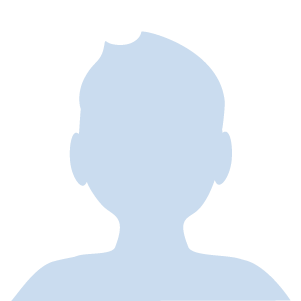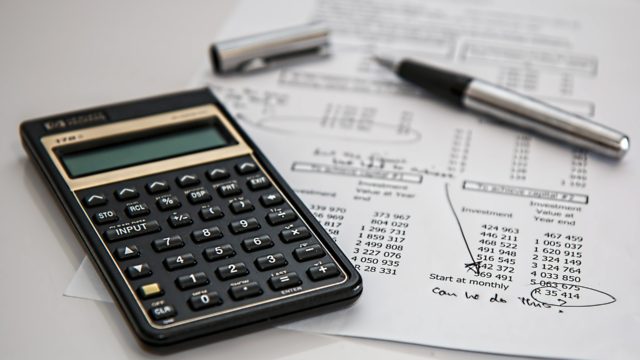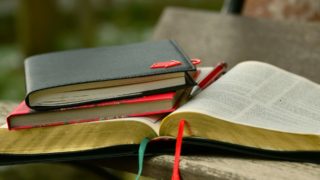税理士業界で転職するか悩んでいる人
『税理士業界での転職を検討しているんだけど、転職で失敗したくないな、、、、避けるべき会計事務所の特徴とかあったら教えて欲しいな。』
こんな疑問にお答えします。
✓この記事の想定読者
・税理士業界に挑戦しようと思っている人
・いまの会計事務所から転職しようと思っている人
・どんな会計事務所があるか知りたい人
こんにちは、税理士のまぐすです。
この記事では、「今すぐ転職すべき、就職を避けるべき会計事務所・税理士事務所の特徴」というテーマで、厳選して10個の特徴を4つのカテゴリーで紹介します。
✓この記事の信頼性
この記事を書いている僕は、元4大税理士税理士法人で働いていました。
また、採用担当マネージャーも担当していたため、様々な税理士業界の事務所の働き方や労働環境についてリサーチしていました。
ここで解説する10個の特徴を知っておけば、間違った事務所に就職・転職することをが避けられますし、今働いている事務所がこれらに該当するのであれば、転職する踏ん切りがつくと思いますよ。
ぜひ最後まで読んで、「税理士業界で働いてよかった!」と思えるような環境を手に入れてもたえたらと思っています。
それでは、紹介していきますね。
📓もくじ
お金に関する特徴
まずは、年収や残業代などのお金に関する特徴について解説します。
特徴①:他の同規模の事務所と比べて明らかに低い
一般に税理士業界は、税金の知識は普通の大学や専門学校、高校では教えられない知識なので、資格の有無や税理士業界での経験年数でスキルが決まってきます。
したがって、業界全体として年収が高いというわけでなく、スキル・経験に応じて年収も上がっていきます。
ただし、今は圧倒的に売り手市場。
たいていの事務所は、優秀な人材を確保するために、いつもより好待遇で入社可能です。
そのため、「同じくらいの規模の会計事務所と比べて明らかに給料が劣る」といった事務所の場合には注意してくださいね。
特に、20代・30代の若手税理士や科目合格者の数がとても少ないので、仮に経験年数や資格を取得できていないとしても十分に良い待遇で迎えてくれる事務所はかなり多くあります。
もちろん、事務所としては、一度採用してしまうと業界で人が少ないからといって、簡単に年収をあげたり下げたりすることができません。
したがって、年収の悩みを解消する方法は、現代の売り手市場では、転職が効果的かつ早急な解決策の1つです。
✓ただし、「時給」という目線を持つことも大事
ただし、単純に年収だけを見て決めるのは少し危険です。
税理士業界の年収は、「時給」という目線を持つことが大事です。
というのも、税理士業界には必ず「繁忙期」というものがあります。例えば申告時期などですね。
それ以外にも、事務所によっては実質的に休みが少ないところもあります。
というのも、税理士は医者や弁護士などと同じく、クライアントが困ったり早急な対応が必要になった場合には、プライベートを削ってでも対応せざるを得ないような状況というのも多々あります。
そういった時期はかなり忙しくなったりもするので、単に年収がいいからといって決めてしまうと「ほとんど帰れないよ、、、」という状況もあるかも。
年収に残業代が含まれているケースもあるので、その点も考慮し、単純に年収だけでなくプライベートとのバランスも考えて、「時給」で考える方が良いかと思います。
特に、税理士試験の勉強を続けている人には、気を付けてくださいね。
特徴②:給料に残業代が含まれる
上記と重複するところがありますが、「残業代が固定給に含まれている事務所は少し注意」です。
現在の税理士業界は、20代30代の若手税理士が少ないことを中心に、労働環境の抜本的な見直しが進められています。
これは、社会的な残業制限の風潮に加えて、4大税理士法人に対する労働基準監督署の調査で問題になったことも影響しています。
そのため、残業が多いことで有名なBig 4税理士法人ですら、2017年ごろからは残業時間を制限し、繁忙期以外、夜間の残業を実質的に禁止しています。
「残業代が年収に含まれる」という状況は、残業時間の管理が十分に行き届いていない可能性があるかも、、、
残業時間の管理がしっかりしていない事務所の可能性がある場合には、積極的にはおすすめできないですね。
現在の売り手市場であればいくらでももっと労働環境の良い事務所はすぐに見つかると思いますよ。
✓とはいえ、残業よりも仕事内容を重視するのもアリ
一方で、もし自分が望むような仕事や案件を任せてくれる事務所であれば、個人的にはすごくいい環境だと思います。
やりたい仕事がやれないことで悩んでいる人も、多いですからね。
特に税理士業界は専門性の高い業界。自分が伸ばしたいスキルを経験できる環境は大切にした方がいいと思います。
明確に自分がやりたい仕事がある人などは、単純に「残業代が固定給に含まれている」ことだけで判断するのではなく、自分にとって何が重要かを考えて判断してくださいね。
特徴③:昇給率が低い
税理士業は専門職であるから、年齢や学歴と言うよりも、業界での経歴や知識量に比例してポジションも上がっていくことが一般的。
そのため、経験や知識量が増えれば増えるほど、そのための勉強を継続しつつも、事務所や売上、部下の管理など、売り上げにつながらない業務も増えてきます。
したがって、本来であればポジションが上がるにつれて、相応に給料が上がらなければなりません。
それにもかかわらず、ほとんど給料が変わらないと言うのは、その事務所で昇進していくことのモチベーションの妨げになりますよね。勉強のモチベーションだって下がるかもしれません。
それであれば、すぐにでも事務所を変えるべきだと思います。
勉強をやめてしまった税理士は、時とともに淘汰されていって、最終的にはせっかく資格を取ったのに仕事がなくなってしまう可能性だって十分にあり得ますよ。
【リクルートエージェント】|一般公開している求人の他、10万件以上の非公開求人がある最大級の転職エージェント。応募が殺到するため一般公開できない重要求人なども取り扱ってます。職務経歴書・履歴書などの書類の添削、独自に分析した業界・企業情報の提供なども無料で行ってくれます。
転職なら【doda】|大手総合転職サイトで税理士業界の転職に一番力を入れているのがdoda。全国多くの事務所の求人あり。
マイナビ税理士
MS-Japan
※リンクをクリックすると、公式サイトへ飛びます。
働き方に関する特徴
つづいて、働き方に関する特徴について解説します。
特徴④:繁忙期以外も帰りにくい
税理士業界は、所得税や法人税の申告期限が重なる1月あたりから3月あたりまで繁忙期である一方で、税理士試験のある7月から9月頃は比較的閑散期となります。
この時期は、多くの人が長期休暇を取得しています。
このように、忙しさばかりが目立ってしまう税理士業界であっても、年間を通してみれば、忙しい時と忙しくない時期があって、ちょうどバランスが取れていると考えられています。
にもかかわらず、繁忙期以外の時期にも休みが取れないと言うのは、理由として考えられるのは以下の2つです。
そもそも人的リソースが足りてない
休暇が取れない理由として、
単純に人が足りていないかもしれません。
繁忙期以外の時期でも休めないということは、繁忙期はそれ以上に忙しくなると思います。
ちゃんと繁忙期以外には長期休暇を取らせてくれる事務所は、いくらでもありますよ。
事務所の文化・慣習
「休暇を取らないことが美徳」「休暇を取れないのが当たり前」という風習の事務所なのかもしれません。
最近の税理士業界の動向としては、働く側にも配慮して、残業を減らす努力や、休暇を取りやすい制度にしたりと、事務所ごとに努力をしています。
繁忙期も帰りにくいというのは、そうした風習が根強く残っているのかもしれないので、しっかりと見極めた方がいいかもしれませんね。
特徴⑤:試験休暇をくれない
多くの税理士法人や会計事務所では、閑散期である7月ごろから、有給休暇と試験休暇を組み合わせて、試験に向けての長期休暇を取得させてくれるところが多くあります。
それらの税理士法人や会計事務所としては、早く試験に合格してもらって活躍してもらいたい!年間通じて業務に集中してもらいたい!と言う思いがあるからです。
また、ちゃんと従業員の将来のことまで考えてくれているといえると思います。
そのため、試験休暇をちゃんとくれないということは、その逆なのかもしれません、、、
というのも、一般的には、従業員が税理士試験に合格すると、以下のような変化があるからです。
理由①:給料が上がってしまう
個人や中堅規模の会計事務所では、税理士に合格していない人は、いわば『勉強中の身』。
最初のころは少し給料が低く、だけど税理士資格に合格して初めて給料が上がると言うことも多くあります。
ただし、もちろん試験に合格したからといって、スキルが一気に爆上げするわけではありませんよね。
そのため、合格を素直に応援してくれる事務所かどうかは、しっかり見極めたいポイントです。。
理由②:転職されてしまう
転職市場においても同じです。
当然のことではありますが、資格を持っていないより持っている方が需要が高まります。
そのため、会計事務所としては、合格されてしまうと転職されてしまうリスクが上がるとも言い換えることができます。
✓【余談】転職しても大事なつながりは続く
転職をためらっている方の中には『事務所には不満があるけど、尊敬すべき上司や先輩がいるから止めにくい』と言う人がいます。
ですが、信頼関係が築けていれば、必ず関係性は続くでしょう。
仮に、頻繁に会う機会がなくなったとしても、税理士業界は非常に狭い業界です。
例えば租税研究会のセミナーや同業他社との飲み会などで会うケースはかなり多いと思います。
したがって、それを理由に転職をためらっていると、とても時間を無駄にしてしまいますよ。
特徴⑥:休暇を取得しにくい
休暇をくれないと言うのは、会社の文化または所長の考えに他なりません。
「特徴⑤:試験休暇をくれない」でも説明しましたが、税理士業界には基本的には繁忙期と閑散期があります。 1年通してこれらのバランスが取れて初めて、企業として成り立つのです。
さらに、現在では税理士業界は圧倒的に売り手市場であるため、Big 4税理士法人を始めとする大半の事務所は、従業員の働き方の改善に力を入れています。
つまり、閑散期にもかかわらず、休暇を取りにくい又は実質的に取れないと言うのは、世間の傾向と逆行しているだけでなく、悪しき文化・伝統とも言えるかもしれませんよ。
そのような文化・慣習は基本的には所長の考えに基づくものです。その時点で、あなたは所長と考えが合わないと言うことになるでしょう。
または、その主張があなたの考えを尊重していない、または気にも留めていないかもしれません。
そうなると、あなたはどんどん時間を無駄にしてしまって、転職市場での価値すらも下がってしまうかもしれません。
【リクルートエージェント】|一般公開している求人の他、10万件以上の非公開求人がある最大級の転職エージェント。応募が殺到するため一般公開できない重要求人なども取り扱ってます。職務経歴書・履歴書などの書類の添削、独自に分析した業界・企業情報の提供なども無料で行ってくれます。
転職なら【doda】
マイナビ税理士
MS-Japan
※リンクをクリックすると、公式サイトへ飛びます。
人間関係に関する特徴
つづいて、人間関係に関する特徴について解説していきます。
特徴⑦:所長・代表と気が合わない
個人の税理士事務所や規模の小さい税理士事務所で働いている人にありがちな悩みとして、その事務所の代表である所長と気が合わないと言うことです。
基本的に、小規模の税理士事務所については、『事務所の慣習や風土=所長の考え』と考えるべきだと思います。
なぜなら、そこで働いている人たちだって、上から評価されない事はやらない、気にしない姿勢になっていくからです。
例えば、部下への指導時間や教育の熱意がその人の評価基準になっているのであれば、その人は積極的に行うでしょう。ですが、もしそれが評価基準に入っていないのであれば、その人にとって時間の無駄でしかないのです。
そしてそれを決めているのは、その事務所の所長です。つまり、所長の考えがその事務所全体の雰囲気や考え方を決めていると言えるのです。
注意点
1日の多くの時間を過ごす職場環境は、あなたの人間的な基礎をも変えてしまいます。
あなたは、知らず知らずのうちに嫌いだったはずの所長や上司に似てくると思います。
ですので、所長と気が合わないとわかれば、その環境が改善される事はありませんので、すぐにでも転職することがお勧めです。
特に、今の転職市場であれば、中規模または大手の事務所へ転職することが個人的にはオススメです。
理由は2つあります。
理由①:今なら中小の会計事務所からでも大手に入ることができる
繰り返しですが、今は圧倒的な売り手市場。特に、税理士または科目合格者が圧倒的に少なく、事務所同士の奪い合いとなっています。なので、大手の税理士法人も、こぞって応募条件のハードルを下げています。こういった環境を利用すれば、もともとは手が届かなかったかもしれない税理士法人にも入れるチャンスがあります。
例えば、以下の記事で業界最大手のBig 4税理士法人を紹介していますので、併せて確認してみてくださいね。


理由②:上司や先輩が嫌だったらいくらでも部署の移動が可能
もし大手の税理士法人に入社とした時に、その直属の上司や先輩が本当に合わなかったとしたら、すぐにでも部署移動することが可能です。
税理士法人としては、今は圧倒的に人材が少なく、かつ、せっかく採用コストをかけて採用したのに短い期間で止められてしまうぐらいなら、部署異動の希望を受け入れるなどして何とかその税理士法人に残ってくれた方がありがたいのです。
なので、入ってすぐに「思っていたイメージと違う」と思っても、すぐに諦める必要はありませんよ。
特徴⑧:上司や先輩が不満ばかり
上司や先輩が、日ごろから日常的に不満ばかり言っている事務所は、すぐにやめたほうが良いでしょう。
税理士業界は、個人個人がそれぞれプロフェッショナルなのです。上司や先輩が日ごろから不満ばかり言っていると言う事は、少なくとも次のいずれかの状態になっていることが考えられます。
懸念点①:プロフェッショナルとして成長できる環境ではない
会計事務所や税理士法人は、一般事業会社のような会社一丸となって戦っていくと言うよりも、個のプロフェッショナルの集まりと考えた方が良いでしょう。
税理士業界に挑戦している人は、税理士科目に合格したとくや税理士に合格した時は、みんな野心があったはず。ですが、今となっては不満を口にしていると言う事は、プロフェッショナルとして自分のイメージとは違ったと言う事かもしれませんよ。
つまり、あなたもその事務所でがんばって耐えてしまっては、プロフェッショナルとしての成長が見込めないかもしれません。むしろ時間を無駄にしてしまい、市場価値を下げてしまうかもしれませんよ。
懸念点②:仕事とその対価である報酬が見合ってない
仕事に求めるものとしては、「給料」や「やりがい」など個人によって様々でしょう。
しかしながら、労働に見合った対価はもらうべきだと思います。なぜなら、対価がやる気や小さな達成感につながるからです。
その点は、上記「お金に関する特徴」に戻ってしっかり確認してくださいね。
仕事内容に関する特徴
さいごに、仕事・業務内容に関する特徴について解説していきます。
特徴⑨:簿記や経理経験、資格を活かせない
こういった悩みを抱えている人は、せっかく簿記や事業会社の経理経験、税理士資格などを有しているのにもかかわらず、それを生かせる仕事がその事務所にないことに対して不安を抱いていると思います。
その場合、その事務所にずっといても、状況が改善される見込みはかなり低いでしょう。
そもそも、高度な税務知識を要するような案件や、複雑な経理処理を求められるような案件がもしその事務所自体になければ、そもそもそのような案件を受注しない方針になっている可能性もあります。
昨今の税法は、仮想通貨や消費税増税などの個人にも身近な税務処理や、租税回避や国際税務などの大手企業向けの税法に関しても、より複雑化しています。
経理処理や関連する税法はより複雑化していますが、もしそういった高度な案件を受注しないとなると、そもそも上司や先輩、所長自体がそのような知識を有していない可能性があります。
もしあなたがそのような仕事をしたいとしても、その事務所にあなたに教えてあげられる人がいない、または誰も教えてあげられないことを理由にそもそも受注していない可能性が高いです。
そういった事務所がこれから急にそのような案件を受注する事は考えにくいので、今のこ売り手市場を利用して、そのような案件を取り扱っている事務所や法人に転職すべきです。
特徴⑩:税に自信がつかない
これは準大手や中堅の税理士法人にも多いことですが、税理士法人にもかかわらず、税金に自信がない社員が多く見られます。
それは、税金の知識を要する仕事を与えてもらえていないことを意味します。
繰り返しではありますが、税務を長年勉強していって、初めてプロフェッショナルと言えると思います。もちろん、それによって自分自身の市場価値も上がっていきます。
ですが、税金の勉強ができない一方で時間だけがすぎてしまうのは、何年やっても転職市場での価値が上がる事はないでしょう。
一般的に、税理士業界は転職経験者が多いので、自分の市場価値を上げることにフォーカスすることも必要だと思います。
▼4大税理士法人に関するnote
4大税理士法人と呼ばれる4つの税理士法人の違いや特徴を、本音や裏話を踏まえて正直にまとめてみました。
4大税理士法人への就職を検討している人は、ぜひご覧くださいね。
さいごに
近年は、税理士試験の受験者数が減っていく一方で、税理士事務所の数が増えてきています。
上記のような特徴を持つ会計事務所は、AIの台頭や会計事務所・税理士法人の乱立、税制の複雑化や応募者の減少により、どんどん淘汰されていくと思われます。
特に、仮に税理士資格を持っていなかったとしても、われわれは『先生』と呼ばれる立場にあることをしっかりと認識し、プロフェッショナルとして成長し続けなければならないと考えるべきだと思います。
その意味で、1人のプロフェッショナルとして、働きやすい・成長できる環境を追い求める事は何ら間違いではありませんよ。こうしたマインドも、この業界で転職率が高い理由の1つかもしれませんね。
そして、これを読み終わった人は、ひとまず転職エージェントに登録してより自分にあった環境を探してみましょう。企業情報がメールで届いたり、無料で転職の相談ができます。いずれも5分ほどで登録できますよ
以下に、この業界の経験を生かした転職におススメの転職サイト3選をまとめてみましたので、合わせて読んでみてくださいね。